妨害に関するルールって他にあるんですか?

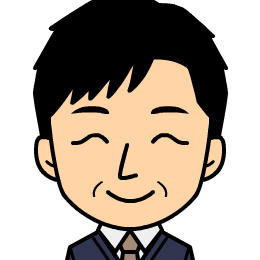
しかし、送球妨害は守備妨害の1つですから、大きな分類としてはその3つで良いと思いますよ。

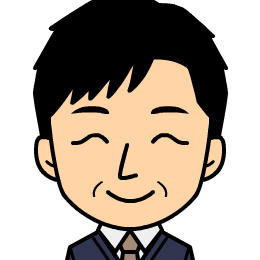
じゃあ、妨害系ルールをまとめておきましょう。
それぞれのルールの概要も書いておきます。
詳しいことは関連記事を見てもらうようにしましょうか。
この記事はこんな人にオススメ
- 野球の妨害系のルールにはどんな種類があるか知りたい
- それぞれのルールの内容を知りたい
- 守備妨害と走塁妨害の優先順位などルール同士の関係性を知りたい
野球の妨害系ルールの種類
公認野球規則で規定されている妨害系のルールを分類すると大きく3つに分けられます。
この記事では、各妨害がどのようなルールかということを説明していきます。
妨害系のルールの種類
- 守備妨害
- 走塁妨害
- 打撃妨害
守備妨害とはどんなルールか?
守備妨害とは、プレイしようとしている野手を妨げたり、さえぎったり、はばんだり、混乱させる行為です。
ただし、これは攻撃側の選手による守備妨害の定義です。
攻撃側の選手以外にも様々な要因で守備が妨害される可能性があります。
公認野球規則では、これらの要因それぞれに対する守備妨害が規定されています。
守備妨害が起きる要因
- バッターによる守備妨害
- バッターランナーによる守備妨害
- ランナーによる守備妨害
- 攻撃側のメンバー(ベンチメンバーやランナーコーチなど)による守備妨害
- 審判による守備妨害
- 観客による守備妨害
- その他、競技場内にいる人による守備妨害
守備妨害が起きたときにに課されるペナルティを書いておきます。
ただし、これはペナルティの原則です。
シチュエーションによってペナルティの内容も変わりますので、そこは注意してください。
守備妨害のペナルティ(基本)
- 妨害をした選手に対してはアウトが宣告される
- 他のランナーは妨害発生の瞬間に占有していた塁に戻される
上で挙げた7つの要因ごとに守備妨害の規定を全て網羅して解説した記事を用意しています。
また、その中で規定ごとに異なるペナルティもすべて記載しています。
守備妨害について知りたい場合は、こちらの記事を読んでください。
-

守備妨害とはどんなルールか?ルールブックに規定される全てを網羅して解説!!
続きを見る
走塁妨害とはどんなルールか?
走塁妨害とは、野手がボールを持っていないか、ボールを処理していない時に、ランナーの走塁を妨げる行為です。
走塁妨害が発生したら、原則としてすぐにボールデッドとなりペナルティが課されます。
ただし、直接プレーに関係していないランナーに対して走塁妨害があったときは、この限りではありません。
走塁妨害が発生したら、次のように処置されてプレーが再開されます。
走塁妨害のペナルティ
- 走塁妨害がなければ達していたであろうと審判が推定する塁まで安全に進塁する
- 走塁妨害発生時に占有していた塁より少なくとも1つ進塁できる
- 走塁妨害されたランナーが進塁することで押し出される前のランナーも次塁へ進塁できる
走塁妨害に関しては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
公認野球規則の定義も確認しながら説明していますので参考にしてください。
-

走塁妨害のルールや定義を詳しく説明!守備妨害とどちらが優先されるか解説付き!!
続きを見る
打撃妨害とはどんなルールか?
打撃妨害とは、投球を打とうする打者を妨害する行為です。
主に、キャッチャーがバッターの打撃を妨害することを想定しています。
よくあるのが、キャッチャーミットがバットに当たるというケースです。
他にはキャッチャーが本塁の前に出てしまった場合も打撃妨害となります。
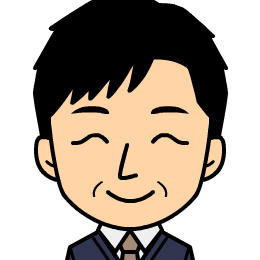
打撃妨害発生後のプレーの処置は、少し特殊です。
なぜなら、「監督の選択権」というものがあるから。
打撃妨害を適用するか、適用しないかを攻撃側の監督が選べるのです。
よって、打撃妨害発生してもインプレーなら、プレーそのまま続けられます。
打撃妨害が発生した時のペナルティは、次の通りです。
打撃妨害のペナルティ
- バッターは一塁への安全進塁権が与えられる
- バッターの進塁によって塁を明け渡すことになったランナーは進塁する
※塁を明け渡す必要のないランナーは、その塁にとめおかれる
打撃妨害もやはりシチュエーションによって、ペナルティの内容が変わります。
詳しく解説した記事を用意していますので、そちらで確認してください。
-

打撃妨害の「監督の選択権」って何?ルールの基本から詳しく解説!!
続きを見る
コリジョンルールについて
コリジョンルールという名称は、プロ野球でよく聞きますね。
コリジョンルールは、走塁妨害の1つに分類することができます。
採用開始当初の2016年は、様々なトラブルがあったので記憶に残っているかもしれません。
コリジョンルールは、キャッチャーのブロックを禁止するルールだと一般には認識されているようです。
しかし、規則を確認するとキャッチャーだけでなく、ランナーの禁止行為も定義されています。
ですので、ランナーとキャッチャー双方が安全にプレーできるようにするためのルールと言えるでしょう。
詳しいことは、コリジョンルールの解説記事を参照してください。
-

コリジョンルールとは?高校野球でも適用されるルールなの?
続きを見る
守備妨害と走塁妨害のどちらが優先される?
野手と走者の接触があったとき、守備妨害になるのか走塁妨害になるのか判断に迷うかもしれません。
公認野球規則には、このような規定があります。
つまり、野手と走者の接触があったとき、その野手に守備機会があれば守備妨害が優先して適用されます。
逆に、その野手に守備機会がなければ走塁妨害が適用されます。
どちらの妨害を適用するかは、守備機会の有無で判断するのです。
これについては、走塁妨害の解説記事の中でも少し触れています。
チェックしておいてください。
-

走塁妨害のルールや定義を詳しく説明!守備妨害とどちらが優先されるか解説付き!!
続きを見る
守備妨害と打撃妨害は表と裏?
例えば、1アウト3塁の場面でスクイズを試みたとします。
キャッチャーは慌てて、前に出てきてボールを捕ろうとしました。
バッターはもちろん、バントしようとしています。
バッターはバットにボールを当てることができましたが、同時にキャッチャーミットも当たりました。
このケースでは、打撃妨害になるのでしょうか。
もし、ピッチャーの投げたボールが「投球」であれば、打撃妨害が取られるケースです。
でも、ピッチャーの投げたボールが「送球」であれば、守備妨害が取られる可能性があります。
(公認野球規則6.01(g)【注4】より)
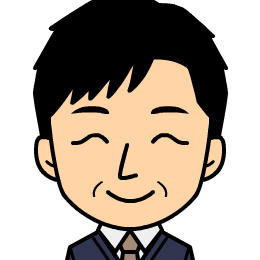
これを理解するには、投球と送球の違いを理解する必要があります。
投球とは、ピッチャーがプレートを踏んだまま本塁へ投げたボールのことです。
送球とは、ピッチャーがプレートを外して本塁へ投げたボールのことです。
ピッチャーがプレーを外すか外さないの違いだけで、他の行為は全く同じです。
しかし、適用される妨害ルールは変わってくるのです。
走塁妨害と打撃妨害のどちらを採用する?
もし、打撃妨害が発生した後、インプレーでプレーが続行したとします。
そのプレーの最中に今度は走塁妨害が起きたら、どうなるでしょうか。
これは、先ほど説明した監督の選択権が関係してきます。
攻撃側の監督が、打撃妨害を適用すると選んだ場合は、打撃妨害として処置されます。
攻撃側の監督が、打撃妨害を適用せずプレーの結果を採用すると選んだ場合は、走塁妨害が適用されるでしょう。
これは、どっちを採用すれば攻撃側に有利になるかで監督が選択できます。
かなり攻撃側に有利なルールになっていますね。
-

打撃妨害の「監督の選択権」って何?ルールの基本から詳しく解説!!
続きを見る
この記事のまとめ
野球の妨害系のルールをまとめて説明しました。
ここでは概要程度しか触れられていないので、詳しくは各関連記事を参照してください。
この記事のまとめ
- 野球の妨害系ルールは、守備妨害・走塁妨害・打撃妨害の3つに分類できる
- コリジョンルールは走塁妨害の1つと考えられる
- 各妨害ルールの間には、どちらを採用するか判断基準がある
妨害系ルールは、ルールの適用が難しいケースが多いです。
どういうときにどのルールが適用されるのか判断に迷う場合が多いでしょう。
ですので、しっかりと内容を把握しておいてください。
守備妨害は、発生し得るケースが多岐に渡ります。
こちらは実際に起こりそうなケースだけを覚えておけばいいと思います。
1つ覚えたら、次覚えるという風に1つずつ理解していきましょう。
なお、ルールの説明は公認野球規則に基づいています。
しかし、細かいところは説明しきれていない部分もあります。
ぜひ、公認野球規則も併せて読んで正しく理解しておいてください。
.jpg)



